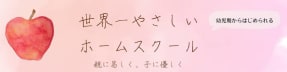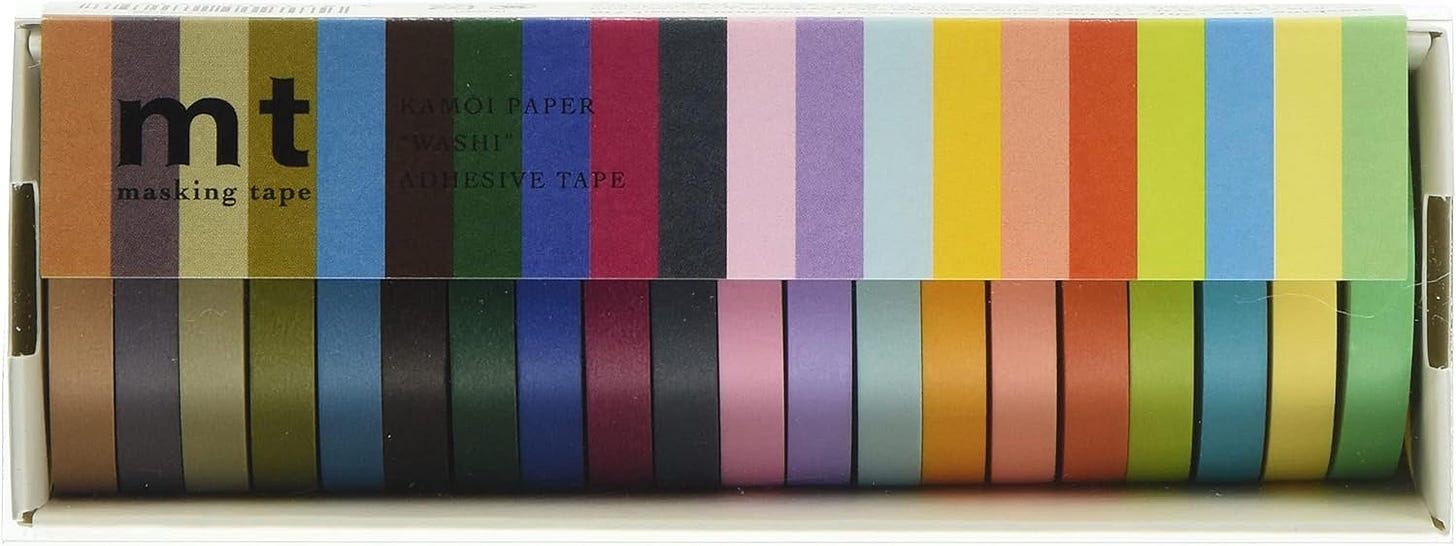ほとんどの人は、毎日子どもに対してイラっとする瞬間があります。そのイライラの原因となる行動のコントロールは重要です。理由は主に2つ。①他の人から好かれることと、②円満な親子関係の構築です。ストレスを減らすことは親子双方にとって重要なのです。
『子育てのストレスを減らす』と題してよくありがちなストレス「食事の時間」「片付け」の問題とその具体的な解決策について全4回の予定で書いていきます。
③5児の年子とでもできる片付け術【前編】←本記事
目次
1.子どもとの生活の2大ストレスを減らす!
・『自分でできる』は親のストレスを減らす良い方法
2.食事のストレスを減らす
【対処法1】物の数を減らして散らかりにくくする
・3つのポイント
【対処法2】遊ぶ場所を決める
・2つのポイント
【対処法3】収納する場所を分かるようにする
・2つのポイント
3.前編まとめ
1.子どもとの生活の2大ストレスを減らす!
私自身が生活していて日々イライラするのは特に食事の時間と部屋にオモチャが散乱することです。
皆さんのご家庭はどうか分かりませんが、我が家には散らかしたり、大人のように集中して食事を終えられない子が4人います。(長女は6歳になり、日常的にイライラするような行動は減りました!)
幼児がいるご家庭ならどれだけ悲惨な状況なのかが鮮明にイメージできることと思います(笑)
もし誰かの家にお呼ばれしたら?児童館やプレイコーナーに遊びに行ったら?
好き放題遊ぶ、散らかす、片づけない。いくら親が後始末を手伝ってくれたとしても、周りにいる人はいい気分ではないでしょう。まずは家庭でできるようになりましょう!
私が見つけた、この2大ストレスを減らす解決法を皆さんに共有したいと思います!もちろん万能ではありませんが、続けるうちに子どもたちがぐんぐん成長していったので、おそらくは皆さんのお子さんにも効果があると思います!
・『自分でできる』は親のストレスを減らす良い方法
自分がイライラする瞬間を考えてみると「なぜ、子どもがすべきことを私がしているの!?」というところに行きつくことが多いです。「なぜ自分で着替えてくれないの?」「なぜ自分で片づけられないの?」。
この、『なぜ自分で』の行動を子どもが自分でできる、またはしやすくなるような環境や状況を作ることで、親のストレスを軽減させることが可能です。
これはモンテッソーリの環境整備の考え方とも繋がるところがあるので、興味のある方はモンテッソーリの環境整備について読まれるといいかもしれません。ここでは、食事に関係する環境と状況の整備の仕方について書いていきたいと思います。
2.片付けのストレスを減らす!
【対処法1】物の数を減らして散らかりにくくする
そもそも、子どもたちがよく遊んでいるオモチャはそれほど多くありません。そして、見える形で収納されていないオモチャは、ほとんどの場合子どもたちは存在すら忘れています。数が多ければ遊ぶのも難しく、片づけるのも難しくなります。いいことはありません。
また、子どもたちは工夫して遊ぶのが上手です!あるものから工夫して作り出すクリエイティブな遊び方は、オモチャの数か少ないからこそ多くなるのです。
では、オモチャの数を減らすにはどうしたら良いでしょうか?
《ポイント1》一軍のオモチャだけを残す
・観察しましょう!
子どもたちが遊んでいるおもちゃを観察しましょう。2週間ほど観察していて遊ばなかったオモチャは必要ありません。
・目的が似たオモチャはありませんか?
よくあるのはブロック系のオモチャのダブりです。そのオモチャで遊ぶ意味を考えてみましょう。目的が似ていたら、どちらかひとつで十分かもしれません。
・親がイラつくオモチャにはさよならする
よく聞くレゴ問題。散らばる、踏みつける、激痛。イライラしないわけがありません。
もしもきちんと遊べない、片づけられない、そして貴方がイライラするのであればサヨナラしてもいいかもしれません。
どうしても残しておきたいのであれば、子どもの目につくところ、でも手が届かないところに置き、貴方の心に余裕がある時に、子どもとしっかり約束してから渡しましょう!
どんなに子どもに良いおもちゃでも、笑顔のママに勝る良さはありません!
・クリスマスを利用する
我が家ではやっていませんが面白いアイディアを聞いたので共有します。
「サンタさんはいらなくなったみんなのオモチャを修理して、来年のクリスマスに他の子にプレゼントするのよ!だから、クリスマスの日にツリーの下に袋に詰めて置いておけば、サンタさんは貴方にオモチャを渡すときに持って行ってくれるのよ。」
もちろん本当の話ではないので、使い方は皆さんにお任せしますが、年に一回、持ち物を整理するのは良いアイディアだと思います。
《ポイント2》ローテーションを組む
オモチャの数が多いのは分かっているけど、どうしても「もったいなくて捨てられない!」「でもまだ使うかも!」と思ったら、子どもの目の届かないところに置き、時々オモチャをローテーションさせましょう。
2カ月もすれば、子どもたちにとってそのオモチャは”新しいおもちゃ”と変わりません。
《ポイント3》オモチャのタイムアウト
もしも親が決めた制限時間までに片づけられなかったら、オモチャをタイムアウトさせましょう!子どもたちの目の届くところに中が見える箱を置きます。片づけられなかったオモチャは1週間、そこに行き、しばらく遊べません。
遊びたいオモチャがない!だから毎回片づけることは重要なんだ!と学ぶきっかけになることでしょう。
【対処法2】遊ぶ場所を決める
子どもたちはオモチャをあちこちに持ち運んで遊びます。もちろん、度が過ぎなければいいのですが、調理中のキッチン、ベッドの中、お風呂場、トイレ、そんなところにはオモチャは欲しくないですよね?
調理中のキッチンにレゴが落ちていて、踏みつける...考えただけでもゾッとします(笑)
遊んでもいい場所を教えてあげましょう。
《ポイント1》家の中に名前をつけておく
指示するときに名前がついていないと...
「この辺りで遊ばないで!」でも、「この辺りって、どの辺り?」子どもには伝わりません。あらかじめ、名前をつけておきましょう!
《ポイント2》目に見えるラインをつくる
さて、名前をつけてもそれがどこまでなのか分からなければ子どもにあなたの考えは伝わりません。そして、ラインが分かりづらければ、そのルールは無視されます。
目に見えるラインを用意しましょう!なんでもいいです。カーペットのところだけ、ソファーよりも前だけ、分かりづらければ床にテープを貼っても大丈夫です。
ルールを作ったら、子どもが実行しやすい環境を作ってあげましょう!
【対処法3】収納する場所を分かるようにする
《ポイント1》全てのものについて収納場所を決める
「何となくそこに置く」は散らかり始めるきっかけです。きちんと収納場所を決めましょう。収納できる場所がないのであれば、おそらくそれは大事ではないものです。【物の数を減らす】でも書いたように、手放すか、ローテーションを組みましょう!
《ポイント2》とにかくラベリング
収納場所を決めたら、きちんとラベリングします。小学生であれば「いつもの場所」が分かるかもしれませんが、それでも正確な場所に収納するのは難しく、頭を使うので疲れます。
幼児でもきちんと収納場所が分かるように視覚化しましょう。
我が家では本は種類ごとに色のついたマスキングテープでマーキングし、戻すべき本棚の場所にも同じテープが貼られています。間違ったところに戻されている本を発見するのも簡単なので便利です。
大きなオモチャは戻すべき場所にそのオモチャの写真を貼って、その上に戻すようにします。小さなおもちゃも箱に入れ、箱を戻すべき場所にオモチャの種類がわかるような写真を貼っておきます。そうすれば、小さな子でもどこに何を戻すのか、親にいちいち聞かなくて済みます。親もいちいち場所を教えなくて済むのでwin-winですね!
子育てのストレスを減らす
③5児の年子とでもできる片付け術【前編】←本記事
最終回は④5児の年子とでもできる片付け術【後編】です。お楽しみに!